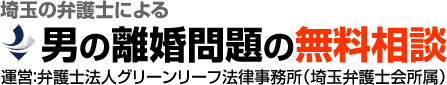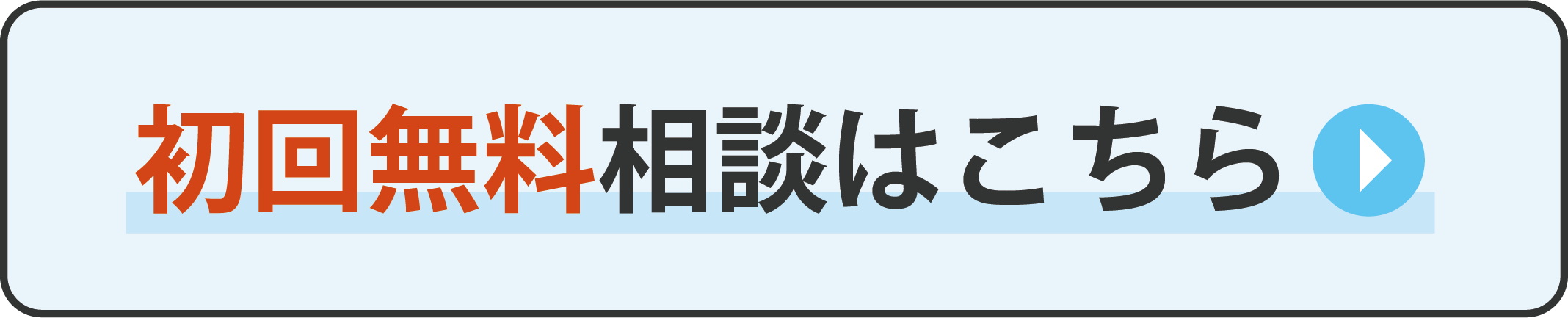紛争の内容(ご相談前の状況)
「元妻から財産分与を求められていますが、相手は私の退職金や預貯金を半分よこせと言っています。しかし、相手は別居中に勝手にお金を使い込んでいたり、隠し口座があるはずなんです。到底納得できません」
依頼者(元夫)は、熟年離婚をした元妻から財産分与調停を申し立てられていました。
調停は3年にも及びましたが、相手方は「財産分与は2分の1(50:50)が原則である」と主張し、一歩も譲りませんでした。依頼者様には、親から相続した資金を元手に増やした株式資産などがありましたが、長年の婚姻期間中に混ざり合ってしまい、特有財産(分与対象外)としての立証が難しい状況でした。
一方で、元妻側には多額の使途不明金や、開示していない口座の存在が疑われました。「原則通り半分」では、依頼者様が汗水流して築いた資産や、親から受け継いだ大切な資産が不当に奪われてしまう。調停での話し合いは決裂し、裁判官が決定を下す「審判」へと移行しました。ここからが、当事務所の離婚専門チームの真価が問われる戦いでした。
交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)
審判手続において、弁護士は「2分の1ルール」を覆すべく、徹底的な調査と緻密な立証を行いました。
「探索的」との壁を突破!多数の調査嘱託を採用させた高度な戦略隠し財産を暴くためには、裁判所を通じて金融機関に照会を行う「調査嘱託」が不可欠です。しかし、単に「怪しいから調べてほしい」というだけでは、裁判所から「探索的である(根拠のない当てずっぽうな調査)」として却下されるのが通常です。
そこで当事務所は、わずかな取引履歴の痕跡や金の流れの不整合を徹底的に分析し、調査の必要性を論理的に構成。数々の戦略を駆使して裁判官を説得しました。その結果、通常であれば断られることの多い多数の調査嘱託申立てを採用させることに成功。これにより、元妻がひた隠しにしていた「隠し口座」の存在や、多額の使途不明金を白日の下に晒しました。「通常なら却下される調査を通し、真実を暴く」。これは、離婚専門チームとしての執念とノウハウを持つ私たちでなければ、決して成し得なかった結果であると強く自負するところです。
夫の特有財産(相続財産)の寄与を立証依頼者様名義の株式について、相手方は「婚姻中に増えたものだから共有財産だ」と主張していました。これに対し弁護士は、過去の古い通帳や取引履歴を執念で遡り、その原資の相当部分が「亡き母からの相続や贈与」であることを主張。完全に分別できないまでも、財産形成に対する依頼者様の個人的な寄与(特有財産性)が高いことを裁判官に強く印象付けました。
「夫からの贈与(慰謝料)」主張の排斥元妻は、別居時に夫から渡された多額の金員(調停が一度起こされており、その際に多額の金員の管理を妻に委ねるという内容となっており、その当時、元妻は代理人弁護士がおり、元夫は弁護士がおりませんでした。)について「贈与されたもの(自分の特有財産)だから分与対象外だ」と主張していました。
これに対し弁護士は、当時の調停調書や資金の管理状況を論理的に紐解き、「あくまで管理を任せただけであり、夫婦共有財産である」と認めさせました。
本事例の結末(結果)
裁判所は、当事務所の主張を全面的に採用し、極めて画期的な審判を下しました。
裁判官は、調査嘱託によって暴かれた元妻による隠し口座や多額の使途不明金、そして株式形成における夫の特有財産の寄与などを総合的に考慮し、「分与割合を2分の1ではなく、3割(妻)とするのが相当である」 と判断しました。
つまり、「夫 70 : 30 妻」 という、実務上極めて異例な、依頼者様に圧倒的に有利な割合での解決となりました。
これにより、依頼者様は退職金や株式などの大切な資産の大半を守り抜くことができ、相手方に支払う金額を大幅に抑える「実質勝訴」を果たしました。
本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
「隠し財産」を暴くには、裁判所を動かす「戦略」が必要相手が財産を隠している場合、裁判所の「調査嘱託」が有効ですが、これを認めてもらうのは容易ではありません。
「探索的だ」と却下されないためには、専門的なノウハウと緻密な戦略が必要です。諦めずに徹底的に調査を尽くす弁護士を選べるかどうかが、結果を大きく左右します。
「財産分与 2分の1」は絶対ではない実務上、財産分与の割合は50:50が原則とされていますが、本件のように、相手方の不誠実な資産隠しや、ご自身の特有財産(相続財産など)の貢献度を証拠に基づいて立証できれば、この割合を大きく修正することは可能です。
「原則だから仕方ない」「調査は無理だと言われた」と諦める前に、ぜひ当事務所にご相談ください。私たちは、依頼者様の正当な権利を守るため、あらゆる手段を尽くして戦います。
弁護士 時田 剛志