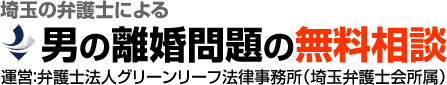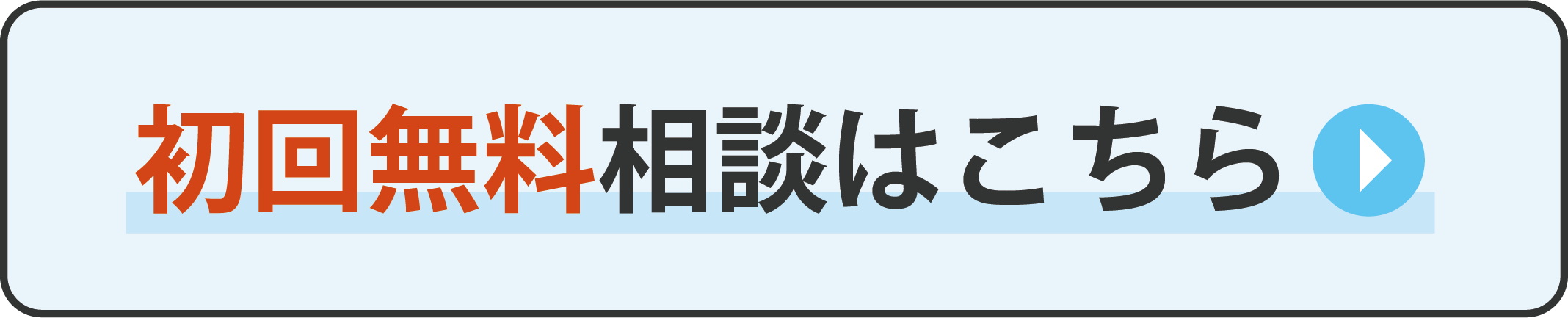紛争の内容(ご相談前の状況)
依頼者(夫)は、妻から離婚調停を申し立てられました。 離婚自体には応じるものの、財産分与、特に自宅不動産の処理が最大の争点となりました。
妻側は、ご自身とお子様がそのまま自宅に住み続けたいと希望していましたが、妻自身の収入は乏しい状況でした。一方、自宅は夫名義であり、多額の住宅ローン(残債約2000万円以上)も残っていました。
依頼者様の最大の懸念は、「離婚後、自分が住まない家のローンを支払い続ける義務だけが残る」「妻が将来ローンの支払いを滞納した場合、銀行から自分に請求が来てしまう」という、一方的にリスクだけを負わされる事態をどう回避するか、という点でした。
交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)
弁護士は、依頼者様の将来のリスクを徹底的に排除するため、法的手法を用いた調停案を構築しました。
単に「妻がローンを支払う」という曖昧な約束で終わらせるのではなく、以下のとおり、法的に依頼者様(夫)を保全する戦略を取りました。
・債務の明確化
妻は夫に対し、住宅ローン残債の全額と同額の金銭を支払う義務があることを確認させます。
・準消費貸借契約の締結
ローンの借り換えが現実的ではなかったため、上記の金銭支払義務を、法的に強力な「準消費貸借契約」として締結させます。 これにより、妻は銀行ではなく、夫(依頼者様)に対して返済義務を負うという法的な形に切り替えました。
・不払時のペナルティ設定
万一、支払いが滞り、その額が2か月分に達した場合は、直ちに「期限の利益を喪失」し、依頼者様は残額の全てを一括で請求できる、という遅滞条項を盛り込みました。
・登記の留保
妻がこの借金を全額完済するまで、不動産の名義移転(登記)は行わず、権利証も依頼者が預かり続けることを条件としました。
本事例の結末(結果)
弁護士による戦略的な交渉の結果、上記条項の全てが盛り込まれた調停が成立しました。
実質的には「妻に、家のローン残債全額を借金として背負わせ、夫を債権者とする」という形を構築しました。
妻は毎月、銀行ではなく依頼者様の口座に返済を行います。 もし支払いが滞れば、依頼者様は残額を一括請求でき、支払えなければ登記を渡さず、家の所有権を主張できるという、将来のリスク回避を目指した内容の離婚となりました。
本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
離婚時に「家を渡す」場合、相手にローンを支払う資力が乏しいと、元々の名義人(夫)が銀行から請求され続けるリスクが残ります。本件のように、単に「妻がローンを払う」という曖昧な約束で終わらせず、法的に「準消費貸借契約」を締結し、夫を「債権者」、妻を「債務者」という明確な関係にしておくことが、将来の不払いリスクに対する防衛策となります。
さらに「登記は完済後」 「不払い時は一括請求」 とすることで、相手の支払いを確実に担保できます。財産分与における不動産とローンの問題は、弁護士の戦略次第で結果が変わります。
弁護士 時田 剛志