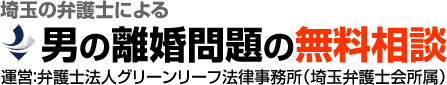幸せな結婚生活を想像して結婚した二人ですが、月日が経つに連れて相手の悪い部分が目に付くようになり、ついには離婚を考えるようになるということがあります。
離婚に至る原因はどのようなところにあるのでしょうか?
今回は傾向から見る夫婦危機について解説をしていきます。
離婚に関する統計

厚生労働省の調査によれば、令和5年の結婚数は約47万組であるのに対し離婚数は約18万組となっており、人口1000人当たりの離婚率は1.52組と計算されています。
男性について、年齢別では30歳代に離婚を経験することが多いとされており、婚姻期間別では結婚から5~10年で離婚に至ることが多いとされています。
地域別では、沖縄県、宮崎県、北海道、大阪府、福岡県の順で離婚率が高くなっており、地位的な差もあるようです。
主要な離婚原因

離婚調停を申し立てる際には、離婚調停を申し立てた動機(離婚したいと考えた原因)についての記載を求められ、離婚原因は以下の13種類から選択する方式がとられています。
①性格が合わない、②異性関係、③暴力をふるう、④酒を飲みすぎる、⑤性的不調和、⑥浪費する、⑦病気、⑧精神的に虐待する、⑨家族をすててかえりみない、⑩家族と折合いが悪い、⑪同居に応じない、⑫生活費を渡さない、⑬その他
裁判所が行った調査によれば、男性側が選択した離婚原因の上位5つは、「①性格が合わない」、「⑧精神的に虐待する」、「②異性関係」、「⑥浪費する」、「⑩家族と折合いが悪い」であり、女性側が選択した離婚原因の上位5つは、「①性格が合わない」、「⑫生活費を渡さない」、「⑧精神的に虐待する」、「③暴力をふるう」、「②異性関係」であるとされています。
弁護士の感覚

裁判所の調査によれば男女ともに「性格の不一致」が離婚原因のトップに位置していますが、この結果はこれまで多くの離婚相談を受けた実感と一致します。
すなわち、配偶者に暴力や不貞行為があるというケースは確かに存在するもののその割合は必ずしも多くはなく、大多数の夫婦は双方の価値観の不一致から離婚を考えているという印象です。
さらにいえば、相談中に耳にする夫婦双方の価値観の不一致の内容についてはある程度の類似性が認められるとも考えています。
夫婦危機に至る原因に関して、暴力や不貞行為についての対策法はそれを避ければよいという分かりやすいものですが、価値観の不一致については夫婦それぞれの結婚観や家族観、これまでの生育環境等に根差す問題であるためその対策は一筋縄ではいきません。
価値観の不一致による夫婦危機を避けるためには?

前提として、将来的にうまくやっていけると思って結婚した相手もあくまで他人であり、すべての面で考え方が一致するわけではないということは認識しておくべきです。
個々人で重要と思うことや物事の優先順位が異なることは当然あり得、それを結婚生活の様々な場面で垣間見ることになります。
必要と思うものにお金をかけているつもりでも他方から見れば無駄遣いと考えるかもしれません、料理は見栄えよりも栄養面と思っていても他方から見れば手抜きと考えるかもしれません、礼儀正しい子どもになってほしいとしつけをしても他方から見ればやりすぎと考えるかもしれません。
このように他人同士が結婚生活を送る上で価値観の対立は日々生じています。
他方にとってやり過ごせるレベルの対立であれば直接的に夫婦危機を生じさせることはないのかもしれませんが、やり過ごすことも一種のストレスとなるためそれが積み重なって夫婦危機が生じる可能性は否定できません。
価値観の相違が夫婦危機に至るケースで多く見られるのが夫婦間のコミュニケーションが不足しているという状況です。
価値観の対立が生じた際、自分はなぜその行動をとったか、それをなぜ重要と思うか、対立を和らげるために双方できることがないかなどのコミュニケーションをとることができれば生じた対立を緩和できますが、それをせずに相手に単に自分の価値観を受け入れるよう強いるという環境が続くと、双方が互いの価値観について寛容でなくなり修復不能な溝が夫婦間に形成されるようになります。
両親がこう言っているから我慢してくれ、金を稼いでいないのだから言うことは聞くべき等の発言はまさに価値観の押し付けにほかなりません。
経験上、女性が本格的に離婚を切り出した後、夫婦が円満な状態に戻る可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
なぜなら、女性は離婚を切り出す時点で、これまでの行動から男性に対して今後も改善する見込みはないという判断をしてしまっているためです。
男性側は離婚を切り出されたタイミングでここを改善するからやり直したいと求めますが、時すでに遅しということになります。
そのような状況に陥らないためには、夫婦双方が日頃から密にコミュニケーションをとり、相手の立場を考えた上で互いの価値観を尊重し、それでも生じてくる対立点については落としどころを見つけるという作業を続けていくことが重要となります。
まとめ

今回は傾向から見る夫婦危機について解説をしてきました。
夫婦危機は日頃の些細な出来事の積み重なりから生じていきますので、些細なことと高を括らず、その都度、真摯に相手と向き合っていくことが夫婦危機の回避につながります。
これは非常に面倒で大変なことですが、夫婦の一方にストレスが溜まり過ぎない環境を作ることが重要となりますので、是非実践いただければ幸いです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
離婚分野について専門チームを設けており、ご相談やご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。