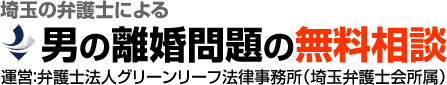配偶者との離婚は非常にストレスのかかるものですが、離婚は人生のゴールではなく離婚後の新しい生活を開始するための通過点に過ぎません。
そのため、離婚が成立した直後から新しい生活をスタートするための様々な準備を行う必要があります。
その中にはお金にまつわる手続が多くありますが、手続を怠るともらえるはずであったお金がもらえなくなるなど損をする可能性もあります。
今回は、離婚後の手続について網羅的に解説をしていきますので、離婚を検討されている方や離婚協議中の方は是非参考にしてください。
離婚直後(離婚成立から1カ月以内)にやるべきお金の手続リスト
離婚時に財産分与で得た財産に関する手続

離婚時に配偶者との間で財産分与について合意した場合、合意した内容に従い名義変更等の手続を行う必要があります。
不動産を取得した場合
不動産の登記簿上の所有者を変更する必要があります。
所有名義の変更には不動産の所有者である配偶者の協力を要しますが、一般的には司法書士が介在することになるかと思いますので、司法書士に対してそれぞれが必要な書類を提供して手続を行います。
不動産を取得する側の必要書類は、離婚後の戸籍謄本、住民票、本人確認書類といったものが一般的です。
なお、登記手続費用の負担(司法書士費用や登録免許税等)をどのように行うかについては離婚時の定めに従ってください。
保険を取得した場合
保険契約の名義変更を行う必要があります。
名義変更には当初の契約名義人である配偶者の協力を要しますが、配偶者が名義変更の旨を保険会社に連絡をすれば保険会社の担当者が対応し、名義変更のための書類等を手配してくれます。
保険を取得する側の必要書類は、本人確認書類、変更後の保険料支払先口座の情報といったものが一般的です。
名義変更後は忘れずに保険金受取人等の変更手続も行っておきましょう。
現金を取得した場合
離婚時に支払金額と支払時期を定めているはずですので、期限までに支払いがあるかを確認してください。
期限までに支払いがない場合には差押え等の手続を行う可能性もありますので、配偶者の勤務先や給与支払口座等の情報を確保しておくことをお勧めいたします。
戸籍、住民票、健康保険、年金に関する手続

戸籍について
役所に離婚届を提出する際、従前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作成するかの選択をすることになります。
お子さんがいる場合には新しい戸籍を作成することになりますが、お子さんを新しい戸籍に入れるためにはお子さんについて氏の変更手続を裁判所で行う必要があります(この手続は離婚前後で同じ苗字を名乗る場合でも必要です)。
住民票について
離婚に伴い転居する場合、役所で住民票異動手続を行う必要があります。
従前、配偶者が世帯主であった場合、離婚後は自身が世帯主となります。
健康保険について
婚姻時、配偶者の被扶養者として健康保険に加入していた場合、離婚に伴い当該保険から脱退することになりますので、自身の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入するか等を選択することになります。
いずれの場合であっても配偶者の健康保険から脱退したことを証明する健康保険資格喪失証明書が必要となりますので、配偶者にその発行を依頼しておく必要があります。
従前の保険証については離婚日を境に使用ができなくなるため、切替えのタイミングで保険診療を受けようとする場合には新たに加入しようとする健康保険に対応を相談してください。
年金について
婚姻時、配偶者の被扶養者として自身で年金保険料の支払いをしていなかった場合、離婚後は役所において国民年金に変更する手続を行います。
自身も厚生年金に加入していたという方は勤務先に離婚の旨を伝えれば担当部署において手続をしてくれるはずです。
配偶者との間で年金分割について合意をしている場合には、年金事務所において分割手続を離婚後2年以内に行う必要があります。
経済生活に関する手続

免許証、パスポート、銀行口座、クレジットカード等について名義変更を行う必要があります。
それに伴い、水光熱費、携帯電話、税金等の支払先の変更を行っておきましょう。
お子さんのための手続

離婚時にお子さんがおり自身がお子さんの親権者となるという場合、お子さんの将来の生活のための経済的支援等について手続を行う必要があります。
養育費について
離婚時に配偶者と養育費について取決めを行った場合、養育費がいつ、いくら、いつまで、どの口座に振り込まれるかを確認しておく必要があります。
養育費は基本的に月々の支払となりますが、振込みが確認できない状況が一定程度続くようであれば、差押え等の対応が必要になる場合もあります。
差押えを行う前提として配偶者に財産がないといけないため、配偶者の勤務先や給与振込口座等の財産状況は把握しておきたいところです。
公的支援について
お子さんを育てる親には各種の公的支援が用意されています。
児童手当について
従前、配偶者が世帯主として児童手当を受給していた場合には役所において児童手当の受給者変更手続が必要となります。
住民票や離婚後の戸籍謄本等を揃えて手続をしてください。
児童扶養手当について
ひとり親援助の一環として児童扶養手当を受給できる場合があります。
手当の金額はご自身の所得額やお子さんの人数により異なりますが、役所において認定申請をしてください(収入が設定上限を超えると支給がされないこともあります)。
申請の際には、離婚後の戸籍謄本、本人確認書類、支払先口座等が必要となります。
就学援助について
小中学校に通うお子さんがいる場合には役所で就学援助の申請を行うことで学用品費、給食代、修学旅行費、医療費などの一部を支給してくれる可能性があります。
【見落としがち】将来のための資産形成

離婚後は日々の生活に手一杯となってしまいますが、同時にお子さんとの将来に向けた資産形成についても考えておく必要があります。
お子さんの成長にあわせた形になりますが、まずは徐々に就労時間を増やし、万一の備えとして一定の貯金を作るというところから始めましょう。
当面の生活に余裕が出てきたら税制上の優遇のあるNISAやiDeCoといった制度を活用することもよいかもしれません。
貯金をしているだけではなかなか資産は増えていきませんが、NISA等の制度を用いて株式投資等を行うことで資産の伸び率をあげることができるかもしれません。
ただ、NISA等については株価下落等のリスクもありますので、あくまで余剰資金で活用することをお勧めいたします。
まとめ

今回は、離婚にあたって損をしないという観点から離婚後のお金の手続について解説をしてきました。
離婚を考えているがなかなか踏み出せないということの大きな要因は離婚後の経済的不安というところにあると思いますので、離婚後の生活についてある程度のビジョンを持った上で離婚方向に進むか否かを検討することが重要です。
ご自身が離婚をした場合にどうなるのかについては専門家である弁護士の意見を聞いてみるということが不安を解消する近道になると思いますので、離婚について思い悩んでいるという方は、是非、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、離婚分野について専門チームを設けており、ご相談やご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。